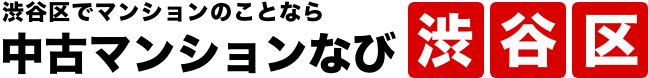中古住宅の診断とは?
中古住宅を売却する際に建物の診断をすることを、インスペクションと呼びます。
2024年4月に、宅地建物取引業法に関連して運用を取り決めている「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」および「標準媒介契約約款の一部を改正する件」が施行されました。
関連記事:購入したお部屋はすぐに不具合が起きても自分で直さないといけない?
主な改正点は?
①契約前に取り行う、重要事項説明の対象となる建物状況調査(インスペクション)の結果は、調査を実施してから2年を経過していないものに延長すること(改正前は1年未満となっていました)。
②①の見直しに関して、標準媒介契約約款における建物状況調査の記載について、建物状況調査を実施する者のあっせん「無」:つまり「できない」もしくは「しない」と表示する場合は、その理由の記載欄を設けるとともに、トラブル回避の観点から、建物状況調査の限界について明記すること
③媒介契約の目的物件が既存住宅である場合、あっせん「無」とするときの理由の記入例について記載する さらに、建物状況調査の活用と併せて、売主等から告知書の提出を求めることにより、買主等への情報提供の重要性を明確化すること
2018年4月の宅建業法の改正によって、
・媒介契約締結時にインスペクション事業者のあっせん可否ついて告知する義務
・インスペクション済であれば、重要事項説明時にその内容について説明する義務
・売買契約成立時にも建物状況について売主および買主が確認した事項を記載した書面を交付する義務
が課せられました。
しかし、インスペクションの普及・拡大による中古住宅の流通の安全を担保するという意味においてはやや実効性に乏しく、現段階でもインスペクションの普及は進んでいない状況にあります。
この状況を打開するために実施されたのが、2024年4月の宅建業法の施行規則の改正で、あっせん「無」と記載した場合にその理由を明記しなければならないことは、インスペクションをなぜ実施しないのかを売主・買主双方から確認される機会を増やすことが容易に想像できることから、住宅売買時にインスペクションを強く意識づけることができるようになるものと考えられます。
2022年に実施された国交省のアンケートによれば、あっせん「無」としているケースは実に74.1%にのぼります。理由についても、あっせんに係る業務の手間が負担である:32.0%、売主・買主のニーズがないと判断した:31.1%、建物状況調査を実施する適切な者がいない・見つからない:30.7%など、否定的な回答が大半で、このままではインスペクションが普及する可能性は極めて低いことが明らかです。消費者に取ってインスペクションの普及はとても重要であることは間違いなく、そのためには仕組みや縛りだけでは難しく、不動産業界全体としての意識改革、そして実務的なサポート体制が必要だとされています。
関連記事:中古マンション売却前に設備の動作をしっかり確認しよう
(初回投稿日:2025年11月7日)